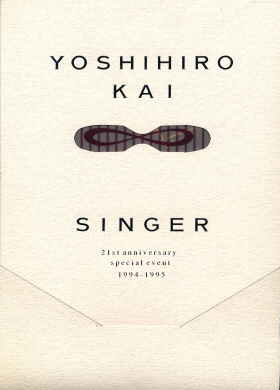|
|
21st Anniversary Special event SINGER 1994-1995
|
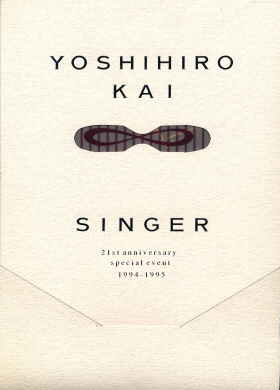
KAI FIVEに実質ピリオドを打ち幕を下ろした甲斐が向かったのは、甲斐よしひろの原点「Singer」であった。
奇しくも20周年になっていたこの94年にあえて20周年記念をぶち上げなかった甲斐は、21周年という区切りでスペシャルイベントを行なった。
それが、この「21st anniversary special event Singer at 武道館」だった。
メインステージは翌95年1月14日に日本武道館で、プレ・ステージとして94年中12月に三郷市文化会館、名古屋でお披露目がった。
プレステージと武道館での決定的な違い・・・それは甲斐バンド復活のニュースだった。
あのバンドが帰ってくる・・・そしてリクエストが各メディアを通じて行なわれ、かつての名曲を・・どれを聞きたいか募った訳だ。
中盤にバンド復活のステージコーナーが設けられ、大森を除く一郎、松藤を迎え4曲を披露するが、久しぶりな「バス通り」などバンドの持てる力、曲の強さも改めて感じたステージだった。
パンフレットは豪華版でA4サイズのポートレート?が30数枚がオシャレなケースに入っている。
パネルにして飾りたい衝動をぐっと押さえて大事に書棚に納まっている。
それだけ、ポートレートにしろ、内容が良い。
そのポートレートの裏にはコメント、対談、寄稿、ディスコグラフィ、ヒストリーなど興味深い記事も多数収録されている。
中でも「「 「うた」を忘れていた甲斐よしひろ」」というタイトルで書かれた稲垣氏の寄稿はぜひ読んで欲しい。
|
|
Top Comment
|
股ぐらをつかまれたような
そんな気分にみんながなってくれたら最高だ。
さあ聞いてくれ。
K A I
|
|
甲斐よしひろとの対話
|
================================
ROCKし続けるためのモチベーション
================================
兼田達矢
デビュー1周年ではなく、21周年。
切りの悪い21という数字が、甲斐よしひろの場合は逆に前のめりな感じを与える。
だから、区切りにするなら・・・ではなく21。
前のめりな区切りを迎えた甲斐よしひろに、ROCKし続けることについて聞いた。
それは、積み重ねられた21年間に変わったこと、変わらないことについての話でもある。
■ “勢い” から ”味”へ。 面白いのはこれからだ!■
兼田◆最近、よくモチベーションという言葉を使いますよね。
”動機づけ” というような意味ですけど。
基本的にはスポーツの解説なんかで使われていますけど、実は人生のいろんな局面でチェックしたくなる要素ですよね。
どういう動機でそんなことしてるの?って。
それに、人生におけるモチベーションってどんどん変わっていったりもするし。
甲斐◆若い時って、テメエが何者かわからないから“僕は何者なんだ”ってことが早く見たいわけよね。
で、一番わかりやすいのは成功することじゃない。
だから”成功するんだ”っていう勢いで行っちゃうわけ。
でも、さらに深化していって続けようとしたら、そういう勢いだけじゃ無理なのよね。
自分がやってることを好きなのかどうかということをもっと明確に見極めるために、ある時には自分を突き放して残酷に冷静に自分がやっていることを見なきゃいけないし、ある時には同化するぐらいにそのものになりきらなきゃいけなかったりする。
そういうことをやった先に面白くなっていくのよ。
つまり、若い頃はテメエを見つけたいっていうのがすごくあるわけだけど、それが時間がたつうちにだんだんわかってくるでしょ。
“僕はこの程度の男なんだ”とか”ま、このへんだろうな”とかね。
だけど、決め込んじゃうと今後の人生のほうがこれまでよりも長いから面白くない。
よし、じゃあもう1ランク上に行ってみるかっていうようなあたりから真剣味ってでてくるじゃない。
兼田◆自分の人生に対する真剣味ってことですね。
甲斐◆そうそうそう。
若い頃っていうのは、自分の人生っていうよりも“行け行けレースが楽しいから参加しちゃった”っていうような感覚のほうが強いからね。
兼田◆そういう意味では、音楽を20年やってきたわけですけど甲斐さんのなかではいろんなことが二まわりぐらいはしてる感じですか。
甲斐◆いやあ、やつと二まわり目に入ったぐらいなんじゃない。
まだ、青臭いよね。
だって、味みたいなことがわかってきたぐらいでしょ。
やつと“勢い”の領域から”味”の領域に入ったところです。
■ 拠りどころ ■
兼田◆薬師寺保栄と辰吉丈一郎の試合(1994.12.4.世界Jrバンタム級タイトルマッチ)を観ていて、物事を高いレベルで長く続けるためのモチベーションということについて考えたんです。
全然違うモチベーションを持っているように見えた二人が実は全く同じような気持ちで戦っているかのようだったから。
甲斐◆確かに、薬師寺と辰吉って表現の仕方は違うけど、ホントに最後の11、12ラウンドを観てると実は考えてることは一緒なんだってことがよくわかるよね。
それは何かっていうと、好きで好きでしょうがないんだっていうところから始まってる。
だけど、それだけじゃ続けられないから、自分なりのオリジナルな発想を入れてくことになるわけじゃない。
恋人作ったり、家族を持ったりみたいな。
自分なりの動機づけを太く持ってるやつがやっぱり続けられるんだよね。
兼田◆で、さらに世界レベルみたいな高いところに行くには、その動機づけの上に科学的な裏付けだったりとか人並みはずれたトレーニングだったりが必要なわけですよね。
甲斐◆自分を抑えてどれだけの人の話に耳を傾けられるか、とかね。
素直さって武器だから。
一流になるか一流半で終わるかの差は、最後はそこなんじゃないかと思ってるわけ。
人の話をちゃんと聴いてないもんね、一流半で終わるやつって。
自分のことを持ち上げてくれる人もいたりするわけだけど、でも真理を突いてることっていうのは耳に痛いじゃない。
だから、そういう痛い部分にどれだけ耳を傾けられるかっていうのは、自分に対してどれだけ残酷で冷静かっていうことになるわけじゃない。
(−流になれるかどうかは)もうそこだけなんじゃないかっていう気がすることがよくあるもんね。
兼田◆ボクシングの話で言うと、ジヨージ・フオアマンがこの間ヘビー級のチャンピオンになりましたけど、この加年ぐらいの間で彼にとっていちばん強い影響を与えた表現っていうのは、キンシャサでモハメド・アリにKOされた一発だったと思うんですよね(1974.103Q世界ヘビー級タイトルマッチ)。
世の中であのパンチの意味を一番素直に受け取ったのが、フォアマンだったんじゃないかって気がするんですけど・・・。
甲斐◆自分のためだけに戦っているんだっていわんばかりのフォアマンと、戦ってるのは僕なんだけど僕だけのために戦ってるんじゃないんだっていうアリの差なんだよね、あれは。
本当は、ていうか、純粋の殴り合いとして考えればフォアマンのほうが圧倒的に有利だし、絶対勝つと、だれもが依ってたわけじゃない。
だけど、ボクシングは精神性なんだっていう型通りの言い方じゃなくて、パンチを繰り出させているもののむこうに何があるかっていうことが実際のパンチの強さ以上に必要なわけよね。
歌も同じで、ミック(・ジャガー)やジャニス(・ジヨプリン)がよく言ってたけど、作品はあくまでも作品であってだれがどう歌うかっていうことが一番肝心なんだっていう。
もっと言うと、人間っていうのは生きてる意味が切実にないと生きられない生き物なんだ、っていうことにもなると思う。
拠りどころだよ、拠りどころがあるか否か。
それが、人によって仕事だったり家族だったりするだけでね。
でないと、続かないよね。
だって、いいことより悪いことのほうが多いんだもん。
真剣にやればやるほど、ね。
いいことって10回に1回ぐらいでしよう。
あとは1回ご褒美もらうための切瑳琢磨だったりするから。
■ 潔 さ ■
甲斐◆あの・・・、ボクシングって”肉を切らせて骨を絶つ”っていう部分だけ見てるとすごく残酷なビジネスだと思うんだけど、その反面あんなに清潔な勝負もないわけよ。
同じように、僕はロックって清潔な勝負なんだということをものすごく口にしてた。
歌を作って歌って生きてくことはしんどいし大変なんだけど、でもいいゼっていうこと。
”肉を切らせて骨を絶つ”みたいな世界なんだけどこれぐらい清潔でワイルドなものはないよっていう言い方だよね、僕の言い方は。
兼田◆そういう意味では、50人、100入っていう規模から始まって武道館でやるようになっても、甲斐さんのなかでは、音楽をやることのモチベーションは全然変わってないってことなんでしようね。
甲斐◆そうそう。
ロックに対するイメージも全然変わってない。
僕のなかでは、たとえば友部正人とか加川良とか岡林信康のある一部の曲っていうのはロックなのよ、完全に。
で、その最高峰がジャックスの早川義夫。
どれも世の中ではフォークと呼ばれていたけどね。
だから、僕が持ってるフォークのイメージっていうのは、たまたまそういう言い方しかないからそう言ってるだけなんだろうなっていう感じ。
実際、当時はロック・ビジネスなんて影も形もなかったわけだから。
で、ベンチャーズとかGSみたいにエレキでガンガンやるみたいなのもあったわけだけど、そっちに行っちゃた方が逆にどんどんロックから離れていっちゃった感じがしてて、ニューミュージックなんて時代になった時にもう一番ロック・ビジネスから遠去かってるイメージだったのよ、僕のなかでは。
そっちに行くの?っていう。
それだったら、僕はあえてロックやりたいって意思を強くしていった感じがあるから。
だから、 「バス通り」みたいな感じの曲でデビューしたわけだけど、そっちへ行ちゃうんだったら僕はどんどんロックしようかなっていうところがあったよね。
兼田◆じやあ最初は、友部さんとか加川さんがフォークと呼ばれてるんだったらオレもフォークでいいよ、ぐらいの気持ちだったんだ。
甲斐◆うん、そう。
だから、僕のなかのロックっていうのはすごくワイルドでハングリーな部分とかファッショナブルな部分とかっていうのがありつつ、ものすごく清潔なものなのよね。
あれだけホントのことを歌っていてしかも仕事になるっていう。
僕は、ボクシングと色物とロックが大好きなんだけれども、この3つってみんなホントのこと言ってるじゃない。
ムードとかニュアンスでわからせる、みたいな曖昧な色合いがないじゃない。
そこに潔さを感じるんだけど、それって僕はすごく清潔な匂いがするんだよね。
だから、すごく残酷なことも厳しいことも汚いことも含めて、あえてロックをやるんだっていうのはいつもあるよね。
|
|
寄稿
|
=============
いくつかのこと
=============
江國香織(作家)
まず、 「スイートキャンディ」。
はじめてこの曲を聴いたとき、なんていいラヴソングだろうと思った。
日なたくさくて退屈で、息苦しいくらい幸福で、レゲエみたいに気持ちがよくて、とろとろととけてしまいそう。びっくりした。
あんなにミニマルなラヴソングは聴いたことがなかったから(いまでも他に聴いたことがない)。
一度聴いただけでおばえてしまい、それから何日か、私はいつもいつも歌っていた。
甲斐さんのラヴソングが好きだ。
どんなのも全部好き。
不幸な匂いのも穏やかなのも、格好いいのも痛々しいのもセンチメンタルなのも、ハードなのも素朴なのも妙にハイなのも。
たぶん声のせいだろう。
甲斐さんの声はいつもヌードなので、どんなラヴソングを歌っても、その向う側にある途方もないかなじみや狂気に、すぽっとまっすぐ届いてしまう。
聴いていて動揺するし、動揺しすぎてとても聴けないときもある。
ラブソングなんだから、そのくらい危険じゃなくちゃ嘘だ。
それから。
いうまでもなく甲斐さんはメロディをつくる天才だ。
甲斐さんのつくるメロデイはたましいを揺さぶる。
「いまのポピュラーミュージックやオーケストラで何よりも重要視されている「サウンド」も、メロディにとって代わることはできない。
サウンドは通りすぎていくけれど、メロディは残ります。」 これはマレーネ・ディニトリッヒの言葉。
デイートリッヒが甲斐さんの曲を聴いていたら、きっと俄然好きになっていたと思う。
これは音楽に限ったことじゃなく、美術でも文学でも一緒だけれど、おなじ時代を共有するというのはものすごいことだ。
私はいわゆるフリークではないので、コンサートにいっても、お腹の底から湧きあがるような太い低い迫力のある声で、「甲斐一つ」と叫んだりはしない。
でも甲斐さんのつくる全部の音、全部の空気を感じたいと思いながらそこに立っている。
甲斐さんという音楽と、時代を共有しているものとして。
ところで、少し前に甲斐さんのファンクラブの会報を見た。
ファンからのいろいろなメッセージが熱っぽくのっていた。
おもしろかったのは、何人もの人が「裏切ってほしい」と書いていたことだ。
裏切ってほしい。
裏切られたい。・・・・・文字にするとすごくアブノーマルなので、私はしばらく会報に見とれた。
裏切ってほしい、と正面きって期待された場合、当然ながらただ裏切ってもそれは期待どおりだから全然裏切りにはならないわけで、裏切ってほしいと期待している人たちをさらに裏切るというのは至難の技だ。
しかも何度も何度も、くり返し裏切り続けるなんていうことは。
でも、大丈夫。
不思議なことに、世の中にはごく少数ながら、どうしても人を裏切らずにはいられない人というのがいるものなのだ。
理屈じゃなくそういう生理をもつ人たち。
そして勿論、そういう人たちのことをアーティストとよぶわけなのだ。
===========================
「うた」を忘れていた甲斐よしひろ
===========================
稲垣伸寿(編集者)
甲斐よしひろがレコード・デビューした年、僕は大学生だった。
クラスメートに甲斐という姓の山口県出身の人間がいて、この男が甲斐よしひろ系の顔をしていたので、音楽雑誌で見かけた甲斐よしひろのことが妙に印象に残っていた。
「バス通り」を聴いたのは、それから2か月目のこと。
若さゆえのほろ苦い思いを少々突き放して歌ったその曲に、僕は不思議なデ・ジャ・ヴュの感覚に襲われていた。
そしてこのときの感覚は、後々まで甲斐の曲を聞くときについてまわるものだった。
甲斐よしひろに初めて会ったのは、札幌か ら帯広に向かう長距離列車の中でだった。
季節は秋の終り、僕は駆け出しの女性週刊誌の編集者として仕事を始めたばかり、甲斐は年の初めに「ヒーロー」のNolヒットを飛ばし、「安奈」をリリースする直前だった。
甲斐はそのとき体調が悪く、確か前日の函館のコンサートでは血を吐いたとも言っていた。
取材は、雑誌の制約もあり、当たりさわりのない人物クローズアップだったが、甲斐は青ざめた顔で速射砲のように言葉を連ね、僕は膨大なテープを東京まで持ち帰ることになった。
甲斐よしひろと初めて音楽の話をしたのは、次の年の初夏、甲斐が初めて出したソロ・アルバム「翼あるもの」をめぐってだった。
ナッシュビルで録音されたアルバムは、他人の曲ばかりをカバーしたもので、いわば甲斐のフェヴアリット・ソング集でもあった。
「サルビアの花」、「マドモアゼル・ブルース」、「恋のバカンス」などなど、収録されている曲のほとんどが自分のフェヴァリットと同じであることを、僕は熱っぽく語ったように思う。
そしてそのとき初めて、甲斐の年齢が僕とわずかふたつしか違わないことに気づいた。
それから、頻繁にではないが、甲斐よしひろとは節目節目で会っている。
たとえば今年の春、甲斐が再びソロ活動に戻ると決意した直後、彼は愛用のアコースティック・ギターを持りて撮影にあらわれた。
そのギターを弾く姿が、甲斐がまだ福岡で歌っていた頃の姿(といっても実際に見たことがあるわけではないが)と重なって、突然僕の中にひとつの言葉が結んだ。
それは「うた」という言葉だ。
少しデ・ジャ・ヴュについて語ろうと思う。
甲斐よしひろの曲に感じるデ・ジャ・ヴュの感覚とは、つまりこういうことだと思う。
あくまで独断ではあるが、甲斐よしひろの音楽ルーツには、橋幸夫や西郷輝彦あたりの歌謡ポップスとそれを継承していったグループサウンズの音が静かに眠っていて、それが時折8ビートや16ビートのリズムに揺り起こされ、曲に微妙な節回しを生む。
甲斐と音楽的に同年代である僕はどうやらその辺にデ・ジャ・ヴュの感覚を感じているのではないかと思う。
正直なことをいえば、甲斐よしひろがバンド活動をやめたことに、ホッとしている。
少なくともアルバム「GOLD」以降のバンド活動は、コンサートをするためにだけ存在していたような気がしている。
アルバムはそのバンド活動の犠牲になっていた。
さきほどの言葉でいいかえれば、「うた」が「GOLD」以降のアルバムからは消失していたような気がしている。
「うた」を忘れた甲斐よしひろ。
では「うた」とは何か。
ひとことでいい尽くすのはひどく難しい作業のように思える。
単純に「メロディー」といえばわかりは早いと思うが、それはまったく違う。
少々わかりにくいかもしれないが、こういういい方がいちばんしっくりくるような気がする、 「自らのうちにある表現しなければいけない何か」。
甲斐よしひろが「バス通り」で歌いたかったもの。
アルバム「翼あるもの」で他人の曲にまで託して表現したかったもの。
甲斐よしひろは、いまバンドという姪桔から開放されて、再びそれらの「うた」に向かって走り始めたように思う。
がんばれ、甲斐よしひろ。
そういえばこの前、甲斐からコンサートに誘われた。
残念ながら仕事でどうしても行けなかったが、ひさびさに活動を再開した早川義夫のコンサート。
甲斐がどんな表情で「サルビアの花」を聴いたか、見てみたかった。
|
|
Musician
|
Guitar
鎌田ジョージ - George kamata
Drums
大久保敦夫 - Atsuo Ohkubo
Bass
萩原”メッケン”基文 - Motofumi [MECKEN] Ogiwara
Keyboard
梁 邦彦 - Kunihiko Ryo
Viorin,Keyboard
武藤祐生 - Hiroo Muto
|
|
|